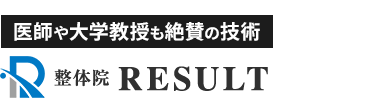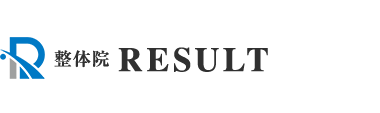坐骨神経痛=腰の圧迫?—その思い込みが長期化を招く
「坐骨神経痛=腰で神経が圧迫されている」と考えると、視点が腰に固定されます。ここに落とし穴があります。実際の現場では、腰だけを整えても変化が薄い方が少なくありません。主語は腰だけではない。お尻から脚へ伸びる一本の坐骨神経は、骨盤・股関節・太もも裏・ふくらはぎと“道のり”を進むたびに、周囲組織から影響を受けます。 土台に小さなねじれや硬さがあると、その“道”に微妙な引っ張りや窮屈さが生まれ、じわじわと負担が集まります。これが「腰を治療しても楽にならない」「一瞬よくても戻る」という現象の説明になります。 私たちが注目するのは、「どこに負担が集まっているか」だけでなく、「なぜそこに集まったのか」です。姿勢・座り方・歩き方・持ち上げ方など、日常のクセは無意識に積み重なります。たとえば、片側で足を組むクセがあると、骨盤はわずかに傾きます。傾いた土台の上に立つと、上半身はバランスを取ろうとして別の部位を緊張させます。こうした小さな積み重ねが、時間をかけて症状の背景を形づくります。 この“背景の地図”を描けないと、施術やリハビリの方向がぶれ、結果として長期化しやすくなります。逆に言えば、腰以外の要素を含む見立てに切り替えた瞬間に、説明と対策が一本の線でつながり始めます。
体の“土台”がつくる負担の集中
骨盤・股関節・筋膜の関係 ここでいう“土台”は、骨盤と股関節、その周りを包む筋膜のエリアです。建物でいえば基礎工事に当たります。基礎がわずかにゆがむと、上の階(腰や背中)にゆがみが伝わります。体でも同じことが起きます。
1)骨盤と仙腸関節
骨盤の後ろ側には仙腸関節があり、左右で微細に動きます。動きが偏ると、骨盤全体のリズムが乱れ、片側にストレスが集まりやすくなります。結果として、お尻の奥の筋肉が緊張し、座面との当たりが変わり、坐骨神経の“通り道”に窮屈さが生まれます。 「座るとお尻の片側がしびれる」「立ち上がる瞬間にズキッと来る」などは、この領域の影響を疑うサインです。
2)股関節の微妙なねじれ
股関節は脚の付け根の大きな関節で、わずかなねじれでも全体のバランスに波及します。内側へねじれた姿勢が続くと、お尻の外側は引っ張られ、太もも裏は張りやすくなります。 この状態では、歩行の一歩ごとに“引っかかる感じ”が蓄積し、神経の道がスムーズに滑りにくくなります。特に長時間の立ち仕事や階段の上り下りで「お尻の奥が詰まる」ような感覚が出るなら、股関節の影響を見直す価値があります。
3)お尻の奥の梨状筋
梨状筋は骨盤の奥にある小さな筋肉ですが、近くを坐骨神経が通り、ここが固くなると刺激の温床になります。 ・長く座ると悪化し、立って少し歩くと軽くなる ・地面の段差でズキッと来る ・腰よりも“お尻の一点”がつらい こうした特徴が重なるとき、梨状筋まわりの影響を点検します。ポイントは、腰を直接いじらなくても症状が動く可能性がある、ということ。ここが「腰だけ見ても改善が進まない」理由のひとつです。
4)筋膜という“つながり”
筋膜は全身を包むうすい膜のネットワークです。硬さは局所だけでなく、離れた場所にも影響を波及させます。ふくらはぎの張りが、お尻の緊張を強めることすらあります。 大切なのは、「局所を点で見る」のではなく、「からだ全体を線で見る」姿勢です。坐骨神経の道を地図にして、どこで渋滞が起きているかを探すイメージが有効です。 画像で「異常なし」でも痛む仕組み:納得のいくストーリー 多くの方が戸惑うのがここです。レントゲンやMRIで「問題なし」と言われたのに、実際はつらい。このギャップはなぜ生まれるのでしょうか。
*画像が得意なもの・苦手なもの
画像は、骨の形や大きな傷、明らかな炎症など“目に見える変化”を捉えるのが得意です。一方で、以下のような“目に見えにくい変化”は映りにくい傾向があります。 関節どうしのごく小さな動きの偏り 皮膚〜筋肉〜筋膜の滑りの悪さ 長時間姿勢による持続的な圧迫・引き伸ばし 体全体のバランスの崩れによる局所の過労 「異常なし」は、“壊れてはいない”の意味に近いことが多いのです。壊れてはいないが、使い方のバランスが崩れている。その結果として痛みが出ている。この視点に立つと、いま起きている体の現象が一本のストーリーになります。
*ストーリーで理解する例
例1:座り仕事の方 片側で足を組む→骨盤がわずかに傾く→仙腸関節の動きがかたより、お尻の奥の筋肉が緊張→近くを通る坐骨神経が窮屈に→長時間座るとしびれ。
例2:立ち仕事の方 片足に体重を乗せるクセ→股関節が内側へねじれやすい→お尻の梨状筋が固くなる→歩き始めや階段でズキッ。
例3:育児・介護で前かがみが多い方 片腕で抱える→肩と骨盤で逆方向のねじれ→腰は無理にまっすぐ保とうとする→お尻の深部が過緊張→座るたびに悪化。
いずれも、画像では“壊れていない”のに、使い方の連鎖によって神経の道が狭くなったり、滑りが悪くなったりしている状態です。だからこそ、エビデンスに基づき体を一本の線で捉える見立てが必要なのです。
痛みの広がりで探す「原因の点」
見立ての順番と現場の観点 症状がお尻→太もも裏→ふくらはぎへと下がっていくとき、どこで渋滞が起きているかを“上流から下流”へ順番に確認します。
1)姿勢とクセの確認
(入口) イスの座り方:浅く座る/足を組む/背もたれに寄りかかる癖 立ち方:片足荷重/つま先が外に流れる 歩き方:腕の振りが片側だけ小さい/歩幅が左右で違う この入口で、負担が集まりやすい方向をざっくり仮説立てします。仮説があると、次の触診や動きのチェックが絞れます。
2)骨盤と仙腸関節の“左右リズム”
立つ・座る・前かがみ・反る動きで、左右どちらが苦手か 片脚立ちで、どちらがグラつくか 座面に当たるお尻の感じが左右で違うか これらは、仙腸関節まわりの“左右リズム”をとらえるヒントです。左右どちらかが苦手なら、その側に負担が集まっている可能性があります。
3)股関節のねじれの方向
内側にねじれやすいか、外側にねじれやすいか 片方だけ動きが固いか 階段の上り下りや、車の乗り降りで違和感が強い側はどちらか ここで、神経の道がどこで引っ張られていそうかを推理します。
4)お尻の梨状筋まわりの緊張
指で押すと「そこ!」という一点があるか 長時間の座位で悪化し、少し歩くと軽くなるか 体をひねるとお尻の奥がズキっとするか この層にサインが集まると、梨状筋の影響が疑われます。
5)下流(太もも裏〜ふくらはぎ)の張りと“戻り” 朝より夕方が重い 歩く距離が伸びると下に広がる ふくらはぎの張りを感じつつ、原因がお尻にある気がする こうした“下流サイン”は、上流(骨盤・股関節・お尻)の影響で道が狭くなり、下流に負担が降りている可能性を示します。 見立ての順番は上流→中流→下流。
この順番を守ることで、原因の点に無駄なく近づけます。
誤解されやすいポイントQ&A(原因理解の補助)
Q1:坐骨神経痛は「ヘルニア」だけが原因ですか? A:いいえ。画像で明らかな異常がある場合もありますが、土台のねじれや硬さが神経の道を窮屈にしているだけのことも多いです。腰の治療で変化が乏しいときほど、腰以外の要素に目を向ける必要があります。
Q2:お尻のマッサージで一瞬軽くなるのに戻るのはなぜ? A:お尻は“通り道”の一部です。原因が骨盤や股関節側にある場合、お尻だけを一時的にゆるめても、上流の渋滞が解消されなければ戻りやすくなります。
Q3:画像で「異常なし」なら我慢しても大丈夫? A:痛みは体のサインです。壊れていなくても、使い方のバランスが偏っている可能性があります。放置すると、別の場所に二次的な負担が広がることがあります。
Q4:年齢のせいで仕方ない? A:年齢は一要素にすぎません。実際には、どう使ってきたかが大きく影響します。説明がスッと通る見立てがあれば、年齢に関係なく変化の余地はあります。
まとめ
結論:坐骨神経痛の主語は「腰」だけではありません。 体の“土台”である骨盤・股関節・筋膜の小さな乱れが、坐骨神経ラインに負担を集め、しびれや痛みを長引かせます。画像で異常がなくても痛むのは、こうした微細な使い方の偏りが写りにくいからです。 見立ての基本は、上流→中流→下流の順に原因の点を探すこと。とくに仙腸関節の左右リズムと、お尻の梨状筋の状態は、説明を一本の線につなげる要所です。 北九州で相談先を選ぶときは、 腰だけで終わらないこと 「なぜ負担が集まったか」をあなたの生活のクセと結びつけて説明できること エビデンスに基づき、体の地図を一緒に描いてくれること この3点を基準にしてください。遠回りを避け、改善までの道のりを短くできます。