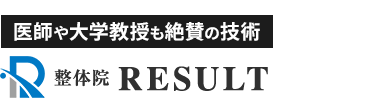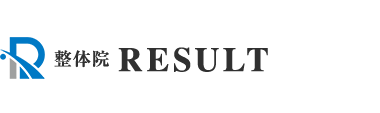① ヘルニアと診断されたけど、本当にそれが原因?
「整形外科でヘルニアと診断されたが、痛みがずっと続いている」
「手術を勧められたが、本当に必要なのか不安だ」
「MRIで異常があったが、痛みと画像が一致しないように感じる」
「ヘルニア」という言葉を聞くと、どうしても「椎間板(背骨のクッション)が飛び出して神経を圧迫しているから痛い」というイメージが浮かびます。しかし、実際には 画像上の「ヘルニア」と症状(痛み・しびれ)が必ずリンクするわけではない のです。
MRI異常=痛み、ではない理由
多くの健康な人にも椎間板の変形がある
実は、痛みがない人のレントゲンやMRIにも、椎間板の膨隆や突出が見られるケースがあります。
つまり「ヘルニアがある=痛みを引き起こしている」とは限らないのです。
② なぜ“ヘルニア”の症状が出るのか?見落とされる原因とは
では、「ヘルニア」の症状、つまり腰やお尻、脚にかけてのしびれ・痛みがなぜ出るのか。その背景にある、構造以上の“見えにくい原因”を見ていきましょう。
腰椎の前弯低下(フラットバック)
背骨(脊柱)は、本来ゆるやかなS字カーブを描くように前弯・後弯を持っています。特に腰椎(腰の骨)はわずかな前弯があって、クッションの役割を果たします。
これが「前弯が減る(平坦になる)」と、椎間板にかかる負荷が大きくなり、特定部位にストレスが集中してしまいます。
結果として、椎間板や関節、靭帯に不安定性が出て、痛みが発生しやすいのです。
骨盤・股関節の可動性異常
腰は骨盤・股関節と密接につながっています。骨盤が後傾・前傾しすぎていたり、股関節の動きが制限されていたりすると、腰椎に過剰な力がかかります。
特に仙腸関節(仙骨と腸骨の間の関節)がずれたり硬くなったりすると、腰まわりの動きがひずみ、腰の神経に負荷がかかることがあります。
内臓・腹圧・軸のズレ
思いがけない原因として、内臓の位置関係、腹圧(お腹の中の圧力)、呼吸や体幹の“軸”が崩れていることも影響します。
たとえば、内臓の下垂や癒着、腹筋・横隔膜の弱化などが、骨格・筋肉・神経のバランスを崩すことがあります。
神経滑走性の低下
神経は体の中で「滑らかに動く」必要があります。足を動かしたり体を曲げたりすると、神経は少しずつ伸びたり縮んだりします。しかし、周囲の筋膜・癒着・癒着によって滑走性が悪くなると、小さな動きでも神経が引っかかり、痛み・しびれが起こることがあります。
これらの要素が絡み合い、「まるでヘルニアのような症状」が出ることは、決して珍しくはありません。
③ 検査では異常なし?それでも痛みがある本当の理由
MRI・レントゲン検査で「異常なし」「軽度」と診断されても、痛みが取れない方は多くおられます。ここで理解しておきたいのは、“検査で映らないから無視していい”わけではないということです。
軟部組織への過剰なストレス
関節包・靭帯・筋膜・筋肉などの組織は、小さな負荷の累積で炎症や微細損傷を起こすことがあります。これらは画像には映りにくいことが多いです。
そしてそれらが神経に近接している場合、神経を刺激し、痛みやしびれを感じさせます。
中枢・感覚過敏の関与
長期間の痛みがある場合、神経や中枢(脳・脊髄)が“痛みを感じやすい状態”になることがあります。
これは「傷害の有無」以上に「痛みを感じやすい回路ができてしまう」状態で、治療の難しさを招くこともあります。
検査だけで安心せず、体全体の“使い方・連動性”を検討することが非常に重要です。
④ ヘルニアは“構造”より“機能”を見る時代へ
近年、世界の臨床現場では「画像だけで診断し、治療を決める」という考え方から、機能・動き・構造の統合的視点への移行が進んでいます。
構造と症状の不一致は常識
多くの研究が、「画像異常があっても痛みと直結しない」ことを明らかにしています。
逆に、明らかな痛みを訴える人でも、画像異常は軽微、あるいは見つからないというケースも多いです。
したがって、構造(骨・椎間板など)だけを見て判断するのは、不十分になることがあります。
機能的な視点の重要性
動きの連動性:関節が滑らかに動くか、筋肉が正しく連動して働くか
姿勢の安定性:骨盤・背骨・体幹のバランスが取れているか
神経の滑走性:神経が自由に動けるか
体軸・圧(腹圧・呼吸):体の中心軸が崩れていないか、圧力が偏っていないか
当院でも、これらを丁寧に観察・評価し、どこに“ズレ”や“癖”があるかを探しています。
多くの場合、腰だけでなく「足首・膝・股関節・骨盤・胸椎」など、離れた部位に原因が隠れていることがあります。
⑤ 手術の前に知ってほしい、本当の体の見方
手術を検討する前にぜひ知っておいてほしい視点と、あなた自身ができることについてお伝えします。
手術は「最後の選択肢」
椎間板ヘルニアに対して、まずは 保存療法(手術以外) が第一選択肢とされるケースが多いです。
飛び出した椎間板が徐々に体内で「吸収」されて改善することもあります。
ただし、排尿障害・著しい筋力低下・我慢できない痛みなどの重症例では手術が早期に考慮されることがあります。
“なぜその状態になったか”を知ること
手術をしても、原因(動き・バランス・使い方)が残っていれば、再発や別部位の痛みが出る可能性があります。
まとめ
“ヘルニア”という言葉が持つ重みは大きく、診断を受けた時には恐怖や不安が湧きがちです。しかし、画像上の異常がすべてではなく、痛みやしびれにはさまざまな“機能的な原因”が関与していることが少なくありません。
椎間板の突出=必ず痛むわけではない
骨盤・股関節・呼吸・神経滑走の異常が痛みの背景にある
保存療法を丁寧に行い、身体の使い方を見直すことが非常に重要
手術は最後の手段として位置づけ、原因を見ないまま進められるべきではない
当院では、「痛みを取るだけでなく、なぜその痛みが出たか」を一緒に探ることを大切にしています。
もし、ヘルニアと診断されて不安を感じているなら、一度構造だけでなく機能から体を見直す機会を持ってほしいと思います。あなたの本来の動き・バランスを取り戻すお手伝いができれば幸いです。