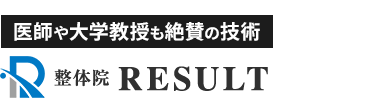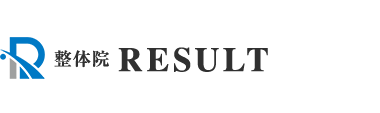「坐骨神経痛」=腰の問題と思い込んでいませんか?
坐骨神経痛と聞くと、多くの方が「腰の神経が圧迫されているのが原因」と思い込みがちです。実際、整形外科では「椎間板が潰れている」「ヘルニアがある」などの説明を受け、湿布や痛み止めを処方されることが一般的です。 しかし――レントゲンやMRIで異常が見つからないのに、お尻から足にかけての痛みやしびれが続く方が多いのも事実です。これは、画像検査だけでは捉えられない「体の構造の問題」が隠れていることを示しています。 痛みの根本原因は、腰ではなく骨盤や股関節、筋膜など「身体の土台」にある場合が多いのです。これらの部位のわずかなズレや硬さが、筋肉や神経にストレスをかけ、結果的に坐骨神経痛のような症状を引き起こすのです。 「腰に異常がないから大丈夫」ではなく、「なぜ痛みが出ているのか」を構造的に見直すことが、根本改善への第一歩です。
『見落とされやすい「骨盤」と「仙腸関節」の不具合』
坐骨神経痛の根本原因を探る上で、見逃されやすいのが「骨盤」や「仙腸関節」の機能障害です。 仙腸関節に微細なズレや動きの制限があると、腰からお尻、脚へとつながる神経や筋肉に余計な負担がかかります。 特に「梨状筋(りじょうきん)」というお尻の奥の筋肉が過緊張を起こすと、そのすぐ近くを通る坐骨神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こすことがあります。 また、骨盤の前傾や後傾といった姿勢の乱れが、仙腸関節の動きを制限し、神経症状の一因となることも少なくありません。
『股関節の歪みと“前方変位”が神経を刺激するメカニズム』
股関節のわずかなズレや変位も、坐骨神経痛に深く関係しています。 特に、大腿骨頭が前方にズレる「前方変位」は、腸腰筋や大腿神経を引き伸ばし、神経に間接的なストレスを与えます。 また、股関節が内旋(内側にねじれる)状態になると、お尻の筋肉が引っ張られて緊張しやすくなり、神経の興奮を助長します。 こうした構造的な歪みは、姿勢や動きのクセ、筋肉のアンバランスなどから生じます。骨盤の前傾や反り腰も、これに拍車をかける要因です。
『腰部のアライメント異常が引き起こす神経の興奮状態』
「ストレートランバー」と呼ばれる、腰椎の前弯(自然なカーブ)が失われた状態になると、腰部の関節や神経に過度な負担がかかります。 本来、腰には適度なカーブがあり、体重や動作の衝撃を分散しています。しかしそのカーブが失われると、腰椎や椎間板に圧力が集中し、神経への慢性的な刺激が起きやすくなります。 また、安定性に関わる「多裂筋」や「腸腰筋」の機能低下があると、骨盤と背骨のバランスが崩れ、坐骨神経に間接的な圧迫が加わるようになります。
『「神経の問題」ではなく「構造の問題」へのアプローチが鍵』
坐骨神経痛の症状は、必ずしも「神経そのもの」が原因ではありません。 骨盤のズレ、股関節の前方変位、腰椎のアライメント異常、筋膜や内臓の緊張――こうした構造的な問題が、神経に間接的なストレスを与えているのです。 つまり、神経そのものを治療するのではなく、神経がストレスを受けない状態に身体を整えることが重要です。 構造の乱れを整えれば、自然と神経の興奮は落ち着き、痛みやしびれも和らいでいきます。 一時的な対症療法ではなく、根本から見直す。その視点こそが、坐骨神経痛に本気で向き合うための第一歩となるのです。