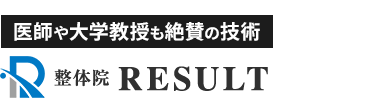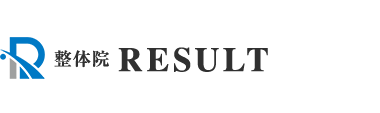【1】「病院では異常なし」でも腰が痛むのはなぜか?
「レントゲンやMRIでは異常なし」と言われたのに、腰の痛みが続く…。そんな経験、ありませんか? 実はこのような腰痛は「非特異的腰痛」と呼ばれ、全体の約85%を占めると言われています。つまり、ほとんどの腰痛は“構造的な損傷が見られない”のです。 だからといって、原因がないわけではありません。むしろ、レントゲンには映らない「姿勢のゆがみ」や「筋肉、関節、内臓の機能低下」が、腰痛の正体であることが多いのです。
【2】腰痛の本当の原因は“腰”にはないことが多い
多くの方が「腰が痛い=腰に問題がある」と思いがちですが、実際は原因が“他の部位”にあるケースが非常に多いです。 たとえば、以下のような例があります: 股関節の動きの悪さ → 腰が代償して負担増 胸椎の可動性低下 → 腰だけが動きすぎて痛み発生 内臓の下垂や癒着 → 腰部の緊張・血流低下を招く 足首の硬さ → 骨盤の動きが制限され、腰にストレス集中 エビデンスに基づき、これらの間接的要因を見逃さないことが、根本改善には欠かせません。
【3】姿勢、内臓、結合組織のつながりと腰痛の関係
慢性的な腰痛を訴える方の多くに共通するのが「円背(猫背)」や「ストレートバック」と呼ばれる姿勢です。 このような姿勢では、腰椎の前弯(S字カーブ)が失われ、椎間板や椎間関節にかかる圧力が一点に集中。その結果、血流が悪くなり、組織の循環が滞り、痛みや疲労が蓄積しやすくなります。 さらに、腹部が圧迫されることで内臓の働きにも影響が出ます。内臓は筋膜や靭帯を介して骨盤や腰椎に付着しており、内臓の可動性低下は腰部の可動性にも影響を与えます。これが「構造的には異常がないのに痛い」という腰痛の背景です。
【4】見落とされやすい“骨盤”と“仙腸関節”の重要性
腰痛の原因として見逃されがちなのが、「仙腸関節の機能障害」です。 仙腸関節は、骨盤と背骨をつなぐ“ショックアブソーバー”のような存在ですが、柔軟性を失うとその役割を果たせなくなります。すると腰椎に過剰な負荷がかかり、慢性腰痛へとつながるのです。 さらに、骨盤のわずかな前後の傾きでも、腰椎の動き方は大きく変わります。 たとえば、骨盤が後傾すると、腰椎の前弯が減少し、ストレートバックに。逆に前傾しすぎると、腰椎が過剰に反って圧迫ストレスが強まります。 こうした骨盤・仙腸関節の評価と調整は、専門的な知識と技術が必要不可欠です。
【5】腰痛改善の第一歩は“原因の正しい理解”から
腰痛は、単なる「筋肉痛」でも「年齢のせい」でもありません。 その多くが「構造ではなく機能」に原因があり、それを正確に見極めることができれば、改善の道筋は大きく変わります。 当院では、構造の異常が見られない慢性腰痛に対し、体全体のバランスや内臓、骨盤・関節の状態まで多角的に評価し、根本原因にアプローチしています。 「どこに行っても変わらなかった…」という方こそ、一度ご相談ください。あなたの腰痛、本当の原因は“腰”ではないかもしれません。
まとめ
「腰が痛い=腰が悪い」と考えるのは、もはや時代遅れです。 北九州で慢性的な腰痛にお悩みの方の多くは、股関節、胸椎、内臓、骨盤など“腰以外の原因”を抱えているケースがほとんどです。 本記事では、画像診断ではわからない「機能的な原因」や、日常姿勢・内臓の影響まで掘り下げてご紹介しました。 慢性腰痛を本気で改善したい方は、ぜひ「エビデンスに基づいた評価」と「体全体を診る視点」を取り入れてみてください。